1回きりの人生を生きていればどん底というのは何回か経験するとは思います。
しかしこのどん底から這い上がっている人に共通する点は成功していると言っても過言ではなくあのどん底を経験しなかったら人生は変わっていたのかもしれないという風に言う人がいるんです。
こういう人たちはあのどん底こそが人生の分岐点だと言ってもいいぐらいまさにどん底は神様の試練だと言ってもいいのではないでしょうか。
どん底というのは悪いイメージがあるかもしれませんし社会的にも本当に色々な意味で叩かれるということがあるかもしれませんがどん底に落ちたということは、そこから先あなたが這い上がるということを考えると成功への始まりだと思いませんか?
私は成功への始まりだと思うんです。
このような暗くてどうしようもない世界で生きていくためにはどん底というのは経験しておいた方がいいのではないかと思います。
どん底に落ちるということは人生で何度もあること
どん底に落ちるということは人生で何度も経験があるように私もどん底は本当に色々な意味で経験してきました。
周りの人になんて理解されないと言ってもいいぐらいですし別に理解されなくてもあなた自身がどん底から這い上がるためには何が必要なのかということを考えてみてください。
どん底から這い上がるということはあなた自身がこれからの人生そのどん底が糧になって新しい事業をするということもいいかもしれません。
もちろんのことながら今は何もない状態から這い上がるということですので当然スモールビジネスになることでしょう。
しかし大事なことはそのどん底の状態から這い上がるということを忘れずにコツコツとやり続けるということが大事で何事も感謝の気持ちを忘れてはなりません。
あなたはどん底に落ちた時本当に周りの環境に感謝した方がいいですし私も周りの環境にすごく感謝しているんです。
このことに気づけるだけでもどん底から這い上がるということの意味がわかってくるんじゃないかと思います。
簡単なことではありませんがどん底から這い上がってきてこれから何をするべきなのかという風に目標は定まった時必ずあなたのターニングポイントというのは近づいてくるでしょう。
ですので人生に何度あるどん底から這い上がってきたらあなた自身がそのたびに自分を律するということをやっていかないとダメです。
どん底から這い上がる人間にはプライドなどない

私はプライドの高い人間ほどどん底に落ちやすいと言っても過言ではなくプライドが邪魔になって本当に何事も感謝できないような人間になってしまうんじゃないかと思います。
人は地位や名誉が欲しいがダメに人を蹴落としてでもその地位に執着するかもしれませんがそんな地位や名誉を捨ててでも私自身はどん底から這い上がりたいです。
そもそも私自身はどん底を経験した時そんな地位や名誉なんていらないという風に思い自分自身はもうこんな生き方をするぐらいだったら自分自身が何をするべきかという風に考えたわけです。
どん底に這い上がるというよりもどん底を経験しているからこそ今はとにかく謙虚に学んでそしてそこから色々なことをやっていくということで一歩一歩前に進んだわけなんです。
どん底から這い上がるためには謙虚な姿勢ですそして今生きていることに感謝するということが重要なんですね。
この謙虚な姿勢が本当にできない人たちというのが増えてきていると言っても過言ではなく私はこういう生き方が一番好きなんです。
ただプライドが高くて本当に人を蹴落としてても自分のことしか考えないような人間よりも、謙虚に生きて誰からも好かれるというのは一番いいかもしれません。
そういう人間はプライドが高くありませんし誰からも本当に親しまれる人間になるでしょう。
だからこそどん底から這い上がるためには何事も謙虚ある人間が一番いいと思います。
這い上がる人間は常に今の環境に感謝している
這い上がれる人はやはり常に今の環境に感謝しなければなりません。
どん底は誰もが経験できるわけでもなくやはり色々な理由でどん底に落ちてしまうということがありその経験こそが人生の糧になると言っても過言ではありません。
私も人生の糧にするという意味ではどん底に落ちること自体が悪いと言っているわけではなく個人的には結果的にどん底に落ちてしまったということが一番最悪だったのかもしれません。
でも1つだけ言えることはどん底から這い上がるというプロセスというのは本当に地味で長いかもしれませんがその長いプロセスの中でも今こうして生きている自分に感謝できるというのはすごくありがたいです。
その間に両親が亡くなり、自分の兄が入院するというような本当に不幸な出来事がありましたがその不幸な出来事にも負けずにこうして生きている自分もこうして生きているんだという風に思うとどん底に落ちているのは自分だけではないという風に自覚できるんです。
私は不幸を何も自慢しているわけではありません。
這い上がる人間は常に今の環境に感謝して今の環境からどうやれば這い上がれるのかということを日々模索して前に進んでいると言ってもいいんです。
今日という日を感謝できる人間になって前に進んでいくということがとても大事なことは言うまでもないですね。
はっきり言えることはどん底に落ちた人間ほど精神が強いということ

どん底に落ちた人間ほど本当に屈辱的な経験や体験などを通じてやはり精神的に強くなっていったのは言うまでもありません。
私も本当に体験的なことをたくさん積んできた中で色々と精神的に強くなってきた部分があったのではないかという風に思っています。
どん底に落ちるということはそれだけ辛い経験を結構してきたと言ってもいいぐらいなのでその経験が自分を成長していると言ってもいいぐらいです。
だからこそ大事になってくるのは自分自身がもっともっと何ができるのかということを考えていかなければなりませんが、どん底に落ちるという経験というのは自分を成長させるためにはある程度必要じゃないかというふうに思うんですね。
誰もどん底になんて落ちたくないですしどん底に落ちないためにもやはり学びの場というのは必要になってくるというわけなんです。
精神を鍛えると言っても普段から食生活に気をつけたりするということもやっていますし私自身もずっとずっとダラダラした生活をしているわけではありません。
ちゃんとした生活をやっているからこそどん底に落ちたとしても自分自身が律するぐらいのことをちゃんとやっているということなんですね。
とにかくどん底に落ちても這い上がれるだけの力はあります。
どん底とは神様からの試練である
どん底とは神様が与えてくれた試練だと言っても過言ではありませんが私は神様が与えてくれた試練であるならば喜んで受けることでしょう。
ここ最近は本当に理解されないというようなことがあったり自分自身が何をやっても空回りするというようなことがあったりということがありました。
お金の心配をしなければいけないのかという風に思われたこともありましたが私は何とかなるなんとかなるという風にアファメーションをやったりというようなこともやっているぐらいです。
世の中は本当に何とかなるんですね。
どん底を経験してもう本当に立ち上がれないというよりになった時に世の中というのは何とかなるという風になった経験もありましたので私は個人的に色々とどん底というのは本当に何とかなるということを考えれば成功への始まりだと言ってもいいぐらいだと思っているぐらいです。
ただ多くの人はどん底を経験していないからかどうかは分かりませんがどん底=悪いことだという風にイメージしていることでしょう。
しかし人生で生きていればどん底というのは何度でも経験するのでそのどん底を経験する中でいろいろなことを学んでいった方がいいですね。
この瞬間に感謝できるあなたがそこにいる

この瞬間に感謝できることというのを考えていただきたいのですが私自身はこのブログに出会えたあなた自身に感謝すると同時にあなたに役に立つ情報をこれからもコツコツと書いていこうと思っています。
私はこのブログを体験型メディアという風に呼んでいるのは体験をしなければ何も書けないということなので結局のところ体験をベースに書いていることが多いですが大切なことは何事も挑戦することです。
挑戦の先に未来があるという風にコンセプトで決めた理由の一つは、これからの時代というのは挑戦する人間こそ成功をもたらすと言ってもいいぐらいなんですね。
言ってみれば挑戦する人間がこれからは成功すると言ってもいいぐらいなのに挑戦しない人間の方が逆に失敗するんじゃないかという風に思っていると言ってもいいです。
この瞬間にあなた自身がどん底に落ちたとしてもまた成功への始まりだという風に思って果敢に挑んでいくということこそ意味があると言ってもいいんじゃないかなという風に思います。
まとめ
どん底にいるというのはつらいですし本当に逃げたい気持ちはよくわかりますが逃げたところで何の解決にもなりません。
どん底に落ちているということはこれ以上もう這い上がることもできませんしここからチャンスだという風に思ってあなたが這い上がるということをやっていけばいいんです。
再スタートを切るという意味でどん底から這い上がるという人もいるかもしれませんが私自身はどん底に落ちても別に気にしません。
何度もどん底を経験し周りの理解も得られなかったというような経験があったからこそリスタートを切れるって言うわけなんですね。
ぜひあなた自身も引きこもりやニートをやるんじゃなくてブログから始めて行って少しずつビジネスを大きくしていきましょう。
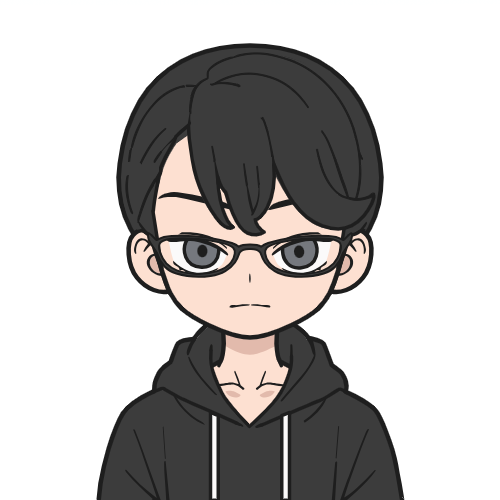
著述家、ブロガー。通称おっさんブロガー。何度もどん底を経験し親の死後
人生観が変わる。コンセプトは「挑戦の向こうに未来がある」ということを
掲げ、日々執筆中。

